今回は年金の老齢給付とは違い、私たち現役世代が明日にでもお世話になるかもしれない障害給付と遺族給付についてです。
15年か20年近く前になるかな、本来20歳になれば国民年金の手続きをして、年金を納付する、もしくは学生猶予制度を利用して追納するといった手続きをするわけですが、何も手続きをしないまま交通事故に遭い障害を抱えてしまった元大学生の特集をしていました。
しかも誕生日を迎えて数日後の事故で障害年金などがもらえないということで、その本人も親も困っているといった内容でした。
それだけに声を大きくして言いたいのは、年金は老齢給付だけではないということ。
確かに払い損といったことがあるのも事実ですけど、明日の事故に備えてきちんと把握しておきたいところです。
障害年金
障害給付には障害基礎年金と障害厚生年金があります。
基本的に老齢給付と障害給付は併給できませんが、基礎年金と厚生年金は併給が可能です。
障害基礎年金
初診日に国民年金の被保険者であること
障害認定日に1級及び2級の障害状態にあること
保険料納付要件(※)をみたしていること
※保険料納付要件は保険料の納付済み期間が2/3以上あることや、これに該当しない場合で、初診日前々月までの1年間に未納がないことといった条件があります。
冒頭にご紹介した事案ですと、国民年金の手続自体をしていなかったので、被保険者にもなってなかったということだったと記憶しています。
仮に猶予期間を申請して認められていれば、追納という形で認めてもらえたのかもしれません。
1級 975,125円(2級の1.25倍)
2級 780,100円
子の加算は2人目まで224,500円、3人目以降74,800円
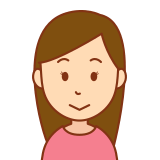
2級だと老齢基礎給付と同額もらえるのですね。
65歳以降の障害基礎年金と厚生年金保険の給付
原則と書いたのは理由があって、65歳以降であれば障害基礎年金、及び障害厚生年金にくわえ、老齢厚生年金を受給できます
ですが、その際も障害基礎年金を受け取っている人は、老齢基礎年金と障害厚生年金を併給することはできません。
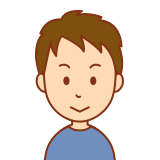
基本的に基礎年金の部分は併給できないと覚えておけばいいかな
障害厚生年金
障害基礎年金は1級、2級の障害者となりますが、障害厚生年金は3級までが給付の対象となります。
また1級、2級の場合には配偶者加給年金も給付されます。
初診日に厚生年金の被保険者であること
障害認定日に1級及び3級の障害状態にあること
障害基礎年金の保険料納付要件をみたしていること
1級 報酬比例部分×1.25+配偶者加給年金額
2級 報酬比例部分+配偶者加給年金額
3級 報酬比例部分のみ(最低585,100円)

むむ、ここでも報酬比例部分が出てくるのか…
遺族給付
遺族基礎年金の受給資格と遺族の範囲
国民年金の被保険者や老齢基礎年金の受給権者がなくなった場合、遺族基礎年金を受給できます。
支給要件は、被保険者、または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上あるものが死亡した時。
また障害年金同様、保険料納付要件は保険料の納付済み期間が2/3以上あることや、これに該当しない場合で、初診日前々月までの1年間に未納がないことといった条件があります。
遺族の範囲は死亡した人に生計を維持されていた子のある配偶者、または子となり、年金額は老齢基礎年金と同じ780,100円となります。
子の加算額は2人目まで224,500円、3人目以降74,800円とこのあたりも障害年金と同様です。
寡婦年金と死亡一時金
こちらは国民年金の制度で、遺族基礎年金が受けられない遺族に寡婦年金と死亡一時金というせいどがあります。
寡婦年金(かふねんきん)
国民年金の1号被保険者として保険料を納めた期間が10年以上ある夫が年金を受け取らずに死亡した場合に妻が受給できる年金で、妻が死亡しても夫には支給されません。
10年以上の婚姻期間があった場合に受け取ることができ、受給期間は妻が60歳から65歳に達するまで、夫の老齢基礎年金額の3/4が受給できます。
死亡一時金
死亡一時金は第1号被保険者として保険料を納付した期間が3年以上ある人が年金を受給せず人死亡し、遺族基礎年金が受け取ることができない遺族に支給されるもので、納付期間に応じた一定額が支給されます。
遺族基礎年金はこのある配偶者ということなので、子のない妻はこちらの死亡一時金が受け取れます。
遺族厚生年金
厚生年金保険の被保険者や老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある人が死亡した場合、遺族基礎年金に遺族厚生年金が上乗せされ受給できます。
さらに一定の条件を満たした妻は中高齢寡婦加算や経過的寡婦加算が加算されます。
中高齢寡婦加算
40歳から65歳までの期間中、遺族基礎年金が受けられなくなった時点で給付されるものです。
40歳以上でも、遺族基礎年金が給付される間は中高齢寡婦加算は停止されます。
経過的寡婦加算
妻が65歳になり、中高齢寡婦加算がなくなっても、昭和31(1956年)年4月1日以前に生まれた妻に、生年月日に応じて支給される制度。
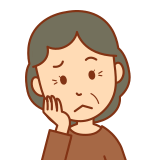
これらも徐々に縮小されるんだろうなぁ
65歳以降の老齢給付と遺族厚生年金
遺族厚生年金を受給している人が65歳になって自分の老齢厚生年金が受給できる場合、老齢基礎年金と老齢厚生年金が満額受給となり、遺族厚生年金は老齢厚生年金に相当する額が減額されます。
まとめ
今回の障害給付や遺族給付といった公的年金を知っておくと、ご自身の生命保険などを検討するときに非常に有利に働きますね。
例えば生命保険には収入補償保険といったものがあります。
会社員の夫が亡くなった場合に月どれくらい必要なのかというのは、毎月の生活費で把握できるでしょうが、それらをすべて保険でまかなおうとすると大変な保険額になります。
そういった意味でも、このあたりを把握しておくのはFP試験に関わらずおすすめです。
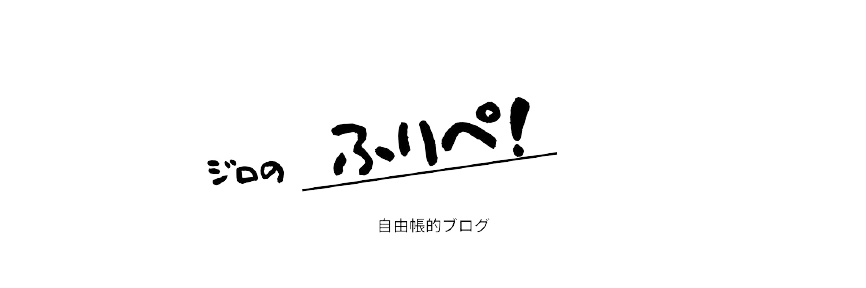



コメント
[…] 年金の種類「障害給付」と「遺族給付」今回は年金の老齢給付とは違い、私たち現役世代が明日にでもお世話になるかもしれない障害給付と遺族給付についてです。15年か20年近く前にな […]