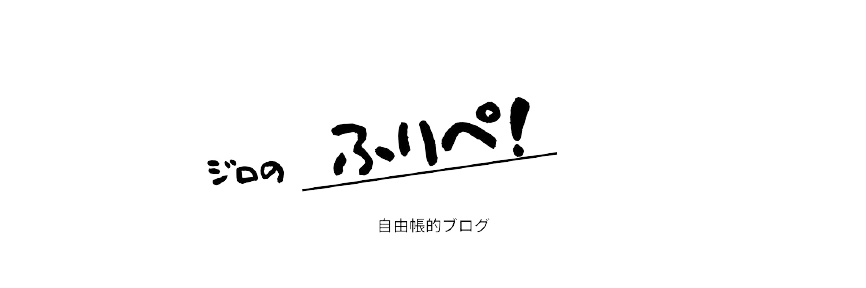年金というと一番気になるのが退職後に手にする老齢給付金。
繰り上げされる、減額されると言われつつも、老後資金の主たる柱になってくれるはずなのです。
公的年金に老齢給付と障害給付、遺族給付とあるわけですが、老齢給付と障害給付といった複数の年金の受給はできません
老齢給付
基礎年金の受給資格
老齢基礎年金は65歳から受給が可能になります。
なお、受給するためには受給資格期間が設けられ、平成29年7月までは掛け金の納付期間が25年以上必要でしたが、平成29年8月からは10年に短縮されました。
受給資格期間は保険料納付済期間はもちろん、免除期間、合算対象期間(カラ期間)を合算されます。
保険料納付済期間 第1号から第3号被保険者として納付した期間
保険料免除期間 第1号被保険者として法定免除や申請免除を受けた期間
合算対象期間(カラ期間) 受給資格期間にはなるが年金額に反映されない期間
このことを考えても、経済的に困窮したときには免除、もしくは猶予申請をしておく必要はありますね。
猶予、免除についてはこちら
年金額
平成31年度の実績で、満額支給額が780,100円です。
免除申請期間がある場合には以下の計算式で求められます。
780,100×(納付月数+免除期間(1/2~7/8))/40年(480ヶ月)
40年払って、1年間(12ヶ月)の全額免除期間がある場合
780,100×(468+12*1/2)/480
となり、780,100×474/480、つまり770,348円という計算になります
繰り上げ受給と繰り下げ受給
基礎年金は原則65歳からとなりますが、本人の希望により繰り上げ、繰り下げ受給が可能です。
一度受給を始めると、一生涯その年金額となり変動しません。
繰り上げ受給すると0.5%×繰り上げ請求月から65歳到達月の前月までの月数が減額となり、繰り下げ受給すると0.7%×繰り上げ請求月から65歳到達月の前月までの月数が増額となります。
仮に60歳から繰り上げ受給すると、0.5%×60ヶ月となりますので30%もの減額となります。
一方70歳まで繰り下げると0.7%×60ヶ月となり、42%もの増額となるわけです。
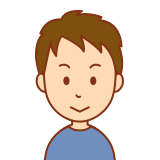
大きいですね…(゜o゜;
うちの会社にも60歳を超えた人がいますけど、満額受給するために65歳まで働くそうです。そりゃそうだよな…
付加年金
付加年金は第1号被保険者だけが任意で加入でき、月400円を納付すれば納付期間に200円を掛けた金額が基礎年金に上乗せされます。
繰り上げ、繰り下げ受給する場合には基礎年金と同様に増減されます。
納付額は400円×20ヶ月となり、8,000円の負担
受給時には200円×20ヶ月となり、4,000円が上乗せされます。
めちゃくちゃお得な制度です。
振替加算
振替加算とは基礎年金に上乗せされるもので、老齢厚生年金の加給年金額の対象になっていた配偶者が、自分の老齢基礎年金が受けられるようになった時に加算されるものです。
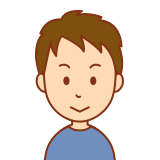
ふむ、よくわからん…また後で振り返り学習しよう
受給要件と開始年齢
老齢給付には60歳から64歳までに受給できる特別支給の老齢厚生年金と65歳から受給できる老齢厚生年金があります。
特別支援の老齢厚生年金は、老齢基礎年金の受給期間を満たした上で、厚生年金加入期間が1年以上、老齢厚生年金は1ヶ月以上必要とのことですが…
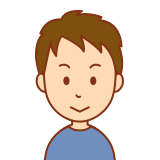
振替加算同様、ますます混乱してるな、後でもう一回戻ってこよう
在職老齢年金
在職老齢年金は年金を受給している人が60歳以降も働きながら受給する老齢厚生年金のことです。
60代前半の場合、総報酬月額相当額と基本月額>28万円の時、年金額が調整され、60代後半以降は総報酬月額相当額と基本月額>47万円のときに年金額(老齢厚生年金)が調整されます。
こうしてみると、高齢者のガードマンが年金を気にして出勤日を調整する理由がわかりますな。
離婚時の年金分割
平成19年4月以降に離婚した場合、夫婦間の合意や裁判所の決定によって、婚姻期間中の厚生年金が分割できるようになりました。
分割上限は1/2となります。
また平成20年5月以降の場合には、合意がなくても平成20年4月以降の第3号被保険者期間について、第2号被保険者の厚生年金の1/2を分割できるようになりました。
婚姻生活を支えていたのに、離婚したら妻は基礎年金しかもらえず生活資金に困窮するとかっていう話があったような気がします。